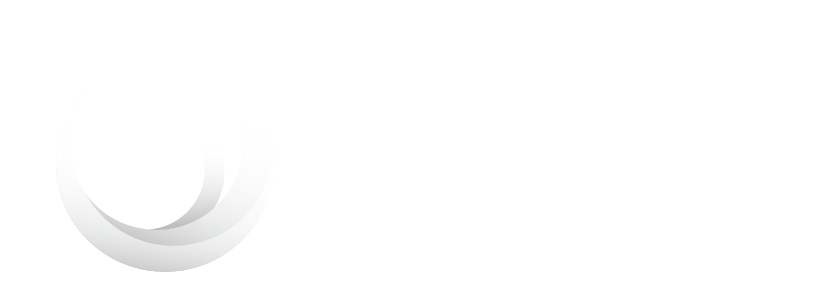環境省が人工光合成のロードマープ、2030年に実用化目指す
環境省は9月5日、「人工光合成の社会実装ロードマップ」を発表した。人工光合成の早期実用化に向けて「技術の性能・規模」「経済性」「制度・インフラ」の観点から、産業レベルで普及させる道筋を体系的に示した。また、代表的な要素技術である電解系と光触媒系の技術は、それぞれ技術要素別ロードマップにまとめた。
人工光合成は、太陽光・水・CO2から燃料や化学品などを生成する技術で、光触媒や光電極を用いた技術が代表的なものになる。なお、水電解も人工光合成に該当するが、すでに実用化されていることから、同ロードマップでは主要対象としていない。生成物は、水素のほか、一酸化炭素(CO)・ギ酸(CH2O2)・メタノール(CH3OH)など炭素1つを含む物質(C1)。エチレン(C2H4)、エタノール(C2H6O)など炭素2つ以上を含む物質(C2)がある。
全体ロードマップでは、2030年までは人工光合成技術の開発の推進フェーズとして、CO2電解技術の実用化に取り組む。2030〜2040年は人工光合成技術の開発〜社会実装フェーズとして、光触媒・光電極、共電解技術(CO2と水を同時に電解して合成ガスを得る技術)の実用化に取り組む。2040年以降は、人工光合成技術を基盤とした基礎原料の量産化と高付加価値物質の製造を目指す。
電解系における実用化の対象技術は、2030年にCO2電解による電解エネルギー変換効率50%以上、2035年にCO2電解+水電解による製造効率60%以上の最終製品製造、および共電解の開発を進める。2040年にはCO+光触媒による最終製品製造、および共電解を利用したメタン製造でエネルギー変換効率80%以上の最終製品製造を目標に掲げる。さらに、2045年にCO2電解によるC1/C2物質の直接製造、2050年にはC1/C2物質由来の最終製品の直接製造を目指す。
光触媒系では、2035年に光触媒による太陽光変換効率10%および光電極による太陽光変換効率25%を目標に掲げる。また、2040年に光触媒・光電極由来の水素とCOなどによる最終製品製造、2045年に光触媒・光電極によるC1/C2の直接製造、2050年に光触媒・光電極由来のC1/C2による最終製品製造を目指す。